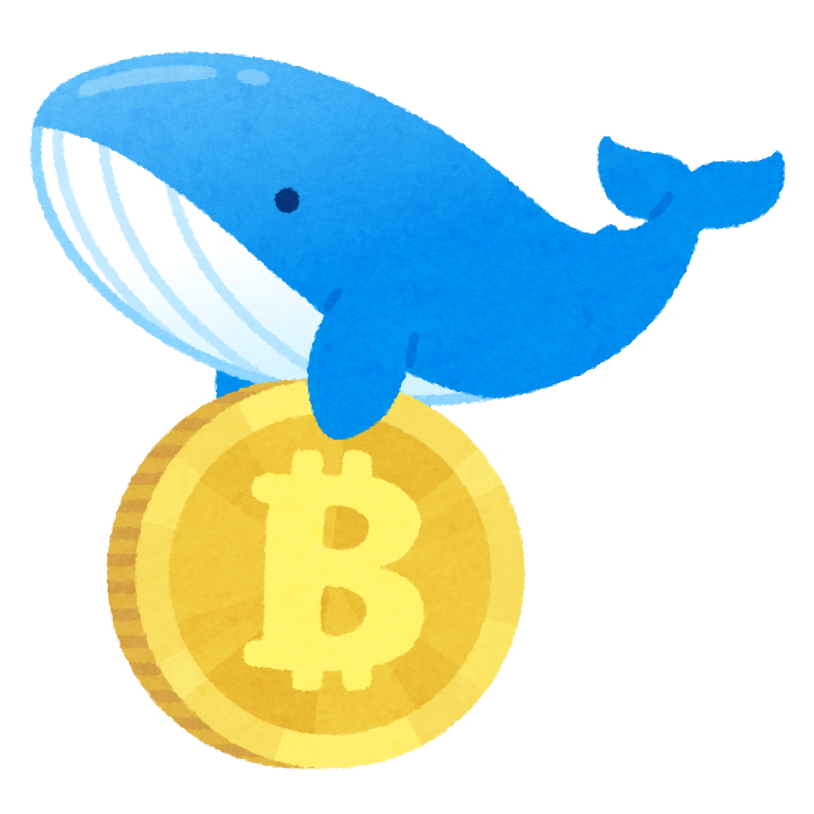作者:珠白だんご
※こちらは寄稿作品です。台本作者は珠白(たましろ)だんご先生です。
お揃いのコーヒーカップを。/珠白だんご
午前六時のファミレスでドリンクバーとフライドポテトを一つ。ケチャップと爪楊枝で皿に絵を描きながらただ過ぎていく時間を横目にくだらない話をしていた。もう夢を語ることにも飽きて、買ってもいない宝くじで現実逃避。ふと、隣のおじさんが飲む珈琲の香りに懐かしい記憶が蘇る。
「ねえ、大人になったら苦くない?」
恨めしそうに父と父が持つコーヒーカップを交互に見ている幼い日の自分。あの頃は大人になれば珈琲は「苦い」から「美味しい」に変わるもんだと信じていた。結局、今もまだ苦くてあまり口にはしていない。数年前までは変わらず毎朝ダイニングに広がっていた香りも、一人暮らしを始めてからはなくなってしまった。それどころか、こうして朝までくだらない話をしながら時間の無駄遣いをしている。そんな自分に後ろめたい気持ちもあって、親との連絡さえも途絶えたままだ。月に一度か二度母からの仕送りがあって、その箱の中に安否を確認する手紙が必ず添えられていた。それを見る度に心がギュッと狭くなる。今の自分を両親が見たらどう思うだろうか。そんなことを毎日のように考えながらこうして友人と何となくの時間を過ごしている。
「バイトの時間だしそろそろいくよ。」
友人はそう言って自分の代金をテーブルの上に置くと、軽く手を挙げあっさりと帰って行った。暫く携帯を眺めて、自分もそろそろ帰ろうかと荷物を手にした時、隣のおじさんに声をかけられ少し驚いた。
「すまないが、これを見てもらえないだろうか?」
おじさんはそう言って鞄の中から細長い箱を出して蓋を開けた。そこには小さな石が付いたネックレスが入っていて、おじさんは少し不安気に尋ねる。
「二十歳になる娘の誕生日なんだが、どんなものがいいのか私には全くわからなくてね。喜んでくれるだろうか……?」
恥ずかしそうに笑いながらおじさんはそのまま話を続けた。
「娘とは一緒に暮らしてなくてね。誕生日にプレゼントをあげたこともなかったんだよ。」
「先月の私の誕生日に娘から連絡があって、おめでとうと言ってくれたんだ。……それはもう、嬉しかった。」
今にも泣いてしまうんじゃないかと思うほど、おじさんの声は震えていて、釣られて目頭が熱くなった。誕生日プレゼントだと言うのにラッピングもされていないそのネックレスはなんだかどの宝石店に飾られている物よりもキラキラして見えた。
「素敵なプレゼントですね。きっと喜んでくれると思います。」
ありきたりな言葉でしか返せない自分の語彙力が情けないなとも思ったけれど、おじさんの顔はパァーっと明るくなって何度もありがとうと言うものだから言葉など案外なんでも良かったのかもしれない。
「こちらこそ、ありがとうございます。」
この言葉に、おじさんは不思議そうな顔をしていたが自分の気持ちはとても軽く、そしてこの時には既に一つの決心も出来ていた。おじさんに会釈をして会計を済ませると少し眠くなった目を一度ギュッと瞑って大きく開く。もし、今日おじさんに会えていなければきっと今から過ごす時間もつまらないままだっただろうなと思う。人と人が出会うのは偶然のようで必然なのかもしれない。
「あ、もしもし母さん?元気?……うん、元気だよ。今度さ……そっち、帰るね。」
風が冷たいこの2月の空は真っ青で、唐突に春が訪れたような日差しを浴びる。家に帰る途中、隣のおじさんの珈琲の香りが頭の中に広がって、コンビニに立ち寄った。レジ横の温かい珈琲を手に取りフッと笑みが零れる。上着の袖を伸ばして両手で握り締めた。ゆっくりと歩きながら珈琲を飲む。
「にがっ……、」
父の笑い声が聞こえた気がした。
どうやら、まだ大人にはなれないらしい。
だけど今は少しだけ、珈琲を飲みたくなる隣のおじさんと父の気持ちがわかったような気がする。
いつか、あの日恨めしそうに見ていた美味しい珈琲を飲める日がやってくると信じて、お揃いのコーヒーカップを買って帰ろう。