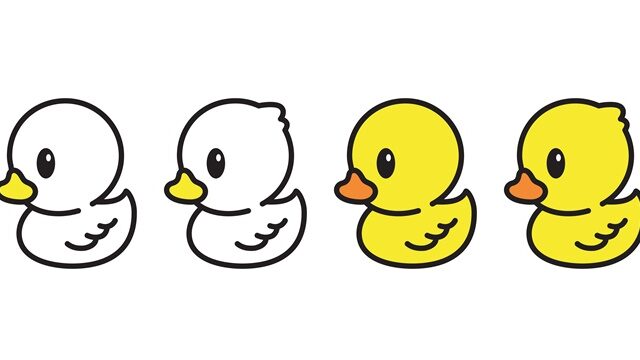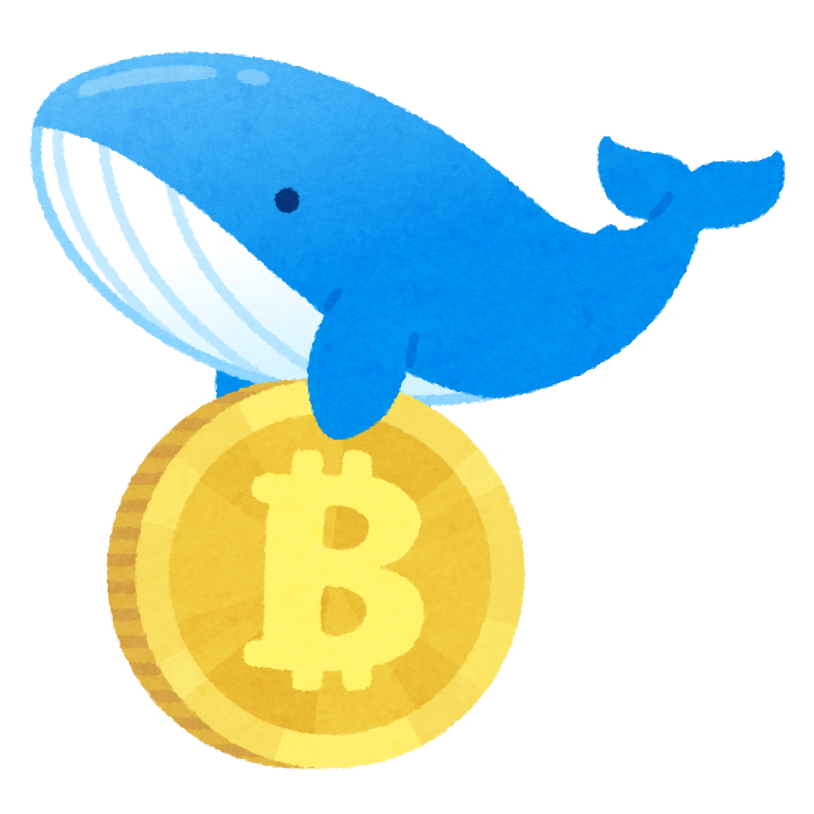作者:道 淨彦(ミチ キヨヒコ)twitter
※こちらは寄稿作品です。台本作者は道 淨彦(ミチ キヨヒコ)先生です。
ガマの呼び声/道 淨彦
そんなに、大した話ではないのですが。私(わたくし)、生まれが島の方でして。ああ、そう、沖縄です。今ではすっかり内地(ないち)の暮らしに慣れてしまったものですから、あまりそういうふうには見えないかもしれませんが。
しかしこれでも、たまには昔のことがなつかしくなって、島に帰ることがあります。
幾年か前のことです。
その日も私は、久々に島の空気を胸いっぱいに吸って、故郷の森を鷹揚(おうよう)に歩いていました。
あそこは森ひとつ取り上げてみてもこちらとはずいぶん違うものです。
かなり空気が湿っていて、それだけに草木が元気そうにしげっていますし、トカゲや鳥もきれいな色をしたものを見かけるとなんだか、つかまえてもいないのにしめた気分になるもので。
ええ、とてもいいところです。
──しかし、そのとき以来もう島には帰っていません。
なぜって、それはとても──とにかく、お話を聞いていただければわかります。
話を戻しましょう。
森の中を散策しながらふと、この美しい自然を帰ってからも思い出したくなって、手ごろな石をひとつ、草をかきわけて拾ったんです。
そのとき傍(かたわ)らにひどく錆(さ)びついて元の形もわからないような鉄の塊が落ちていたのをよく覚えています。ええ、あれも今思えば──いえ、きっと思い過ごしでしょう。きっと──うん、そんなはずは──。
ああ、すいません。少し嫌なことを考えてみると、背筋が凍るようなところまで、思い当ってしまうこともありますね。さあ、続けましょう。
石は、そのままリュックの奥の方にしまいました。そうして、さてそろそろ宿に帰ろうかというところで、木々の間から覗かれる真っ黒いものに目を奪われたんです。それは、遠目に見ても人が幾人も入るぐらい大きくて、丸い形をしていました。
何故だかよくわかりませんが、私はどうにも気になってしまったんです。少し近づいてみれば、そこには大きな洞穴(ほらあな)がありました。
はてこんなところに洞窟なんぞあったかな、道に迷ったのだろうかと、その穴をじっとみながら考えているうちに、私はふと、自分の喉がひどく乾いているのに気づきました。
ええ、そして──ちょうどそのときでした。洞窟の奥の方から、滴の垂れる音を聞いたのは。
──信じられないくらい、水を求めていたものですから、手荷物の中の水筒のことまで忘れて、私はまっすぐ暗闇の中へこの身を投じたんです──ええ、本当に、遠くまで投げやるような勢いでした。
今まで一度だってないほどに必死だったものですから、あんまりそれからどういうふうに降りていったのか、自分でもわかりませんが、そうしているうちに、私は不思議な明かりの下にいるのに気が付いたんです。
ああいえ、そこも同じく穴は穴でしたが、入り口があんなに大きかったのに、私の目の前に続いている道は、人がちょうど並んで二人歩けるほどの広さしかないのが不思議でした。
しかしそんな考えは、すぐに例の渇きが鎌首をもたげて、とにかく吹っ飛ばしてしまったんです。
「進まなきゃならんのだ、進まなきゃならんのだ」と、ただそれだけを考えて前に進んでいると、たまにものすごく背中が熱くなったり、とてつもない風に押されて体がふわりと前に飛び出たりして
──あれも、一体何だったのか──とても見当なんて──いや、つかないわけでもないんですが、口に出すのがこんなにそら恐ろしいこともないんです。どうか、それ以上お尋ねにならないでください。
ええ、それでは、また……続けましょう。
さらに奇妙なのは、その洞窟に入ってそれまで人っ子一人見当たらなかったのに、そこが妙に生臭かったことです。変な、汗と、なんといいますか、その、便(べん)が、境もなくなるほど交じり合ったものに、うえから鉄の粉をまぶしたような、不愉快な臭いでした。それが、体の周りにねっとりまとわりつくみたいに、私を包んでいるんです。
なんだか、しばらくその空気を吸っていると私も股のあたりからこう、肉が錆(さ)びてぽろぽろ落ちていっているような気持ち悪い感覚がしてきました。
しかし、喉はあいかわらず乾くんです。もう入る前よりずっとカラカラで、ろくにものも考えられませんでした。
とにかく前に足を進めて、洞窟の奥まで行こうとしたんです。
そうして、もう、何か飲まなければ干からびてしまいそうなぐらい口の中がひりひりしていたぐらいになって、やっと私は、向こう側から、近づいてくる人影を見つけられました。
こんなむさくるしい中を、手慣れた様子できびきびと歩いてきていましたから、そのひとの風貌はすぐ明らかになりましたよ。ワイシャツと、下にもんぺを履いて杖をついた、女生徒さんでした。
──ええ、しかし、いまどき妙な格好でしょう。ですが、そんなことはもう、私にとってはどうでもよいことでした。水、水、そればかりでしたから──。
ふらふらしていた私を見て、女生徒さんはすぐに「なにをしてらっしゃるんですか」と口を開かれましてね。
私は、死人のうめき声みたいなガラガラのだみ声で、「水」とだけ言ったんです。
すぐさま「この先に、そんなものございませんのよ」と返されて途方に暮れたような気持でいると、「わたくしもちょうど外に御用がありましたから、ついていらっしゃってください。こんなムシムシするところでは、一口水をのんだところでしようがないでしょう」と、優しく声をかけてくださったので、私は、拝みたくなるような気持ですっと踵を返してしまいました。
「危なかったわ。この先には、兵隊さんがたくさんおりますから、このままいっていれば、殺されてしまうところでしたのよ」と、私を先導する彼女は言うものですから、こんな場所に某国軍の駐留基地なんて、あった覚えは、なんて思案もしてみましたが、それ以上に妙なのは、彼女が地面につきもせず持っている杖でした。
それで、お若いのに、どうしてそんなものをもっているんですか、と訊くと、「もうじき日も落ちます。外には、『いやなもの』が、たくさん転がっておりますから、それを踏んずけちゃいけませんものね。こうして、杖で足元を確かめるんです」と言うばかりで、私は腑に落ちないわだかまりをもやもや抱えたまま彼女のあとを歩いていきました。
他にも、変なことをたくさん言われました。
「こんな場所ですから気が触れてしまう方も大勢いらっしゃいますけど、どうか気をしっかりもって、もし、くるってしまっても決して、そこらに落ちているものを口に入れたりはなさらないでくださいましよ」とか、「洞窟を出るまで、振り向いてはいけませんよ」とか。
しかし、その方の声には、どうも私の気持ちを安らかにしてくれる不思議な力があるように思えてなりませんでした。さっきまでとは逆向きにずんずん進んでいくごとに、喉の渇きもやわらいで、頭からぽんと抜けていってしまったぐらいのものです。
そうこうしているうちに、とうとう元の場所へ私は戻ってきました。
女生徒さんが満足げに笑いかけてきて、「それでは、わたくしはこれで」と洞窟の中に戻ろうとしましたから、「ご用事があるのでは?」と問いかければ、「もう済みました。早くお帰んなさい」と答えて返したのに、私の口をついて出た返事は──笑わないでいただきたいのですが、本当に、無意識に、私は──「はい、姉さん」と、そう言ったんです。
そのあと、すぐにハッとして、私はあの顔が、戦時中に学徒隊で動員され死んだと聞かされた、姉の写真にうり二つだったことに気づきました。
なんだか、嬉し半分で、しかし、真っ暗になった森が、ゾッとした気持ちの方を大きくしたものですから、私は怖気づいて一目散に宿へと駆け戻りました。
いえ、島にはもう、と確かに言いましたが、そこから行ってないわけではありません。とはいっても一度だけなんですが、とにかく一度また翌朝、その森に出向いたんです。
途中までは、きれいで蒸し暑い、いつもどおりの島の森でした。が、しかし、たったひとつ、獣道のうえに転がっていた、擦り切れて、ぼろぼろになった布きれの染み、たったそれだけ、その一点だけなんですが、それが目に留まったとたんに、私は、他のものが見れなくなってしまいました。
「なぜ、こんな人気(ひとけ)のない森にそんな、人間のものが落ちているんだろう」と、考え始めたら腹の底から蛆がわいてくるような気味悪さがどっと押し寄せてきて、昨日、あの『姉』と別れてから感じた、背筋にひんやりとミミズが通っていくような感覚になるので、また同じように、すぐに帰り支度を整えて、もう島を離れました。
ええ、それっきりです。
嘘ではないんですよ。御覧なさい、これがそのとき持ち帰った石です。私はこの石から、なんだか不思議なあたたかさと、こわさを感じるんです……。