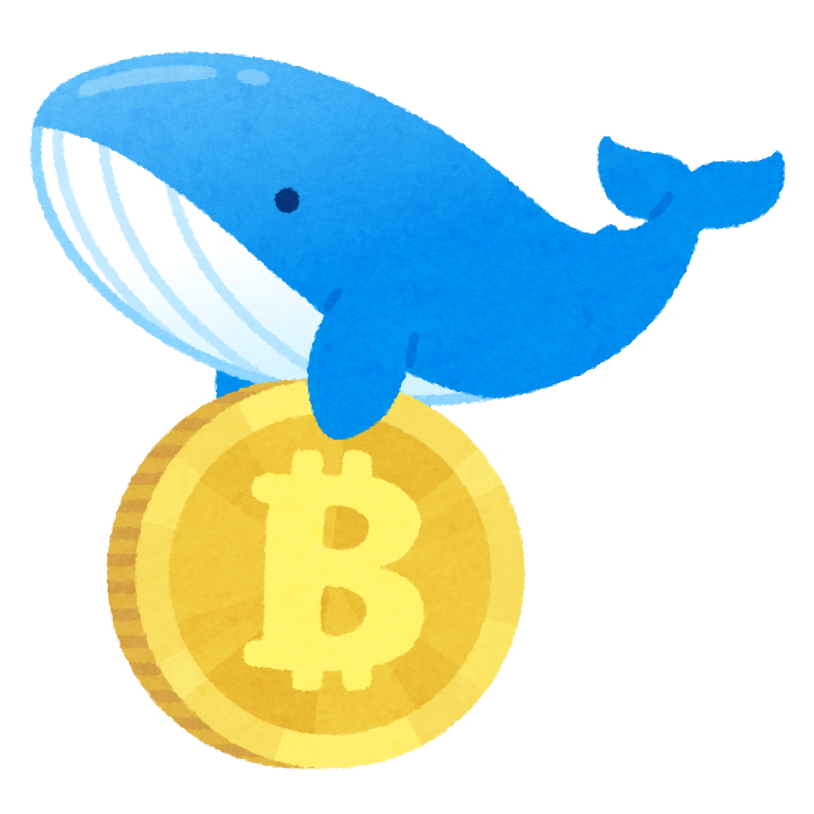日常の切り取り。約1000文字。所要時間:3~5分
初春の三竦み/筆先ちひろ
定期的に届く段ボールの封を開け、奈津美はにんまりと口角を上げた。古臭い紙袋の匂いが立ち込めるその箱の中身は、5kgの米と、それから、形の悪い野菜。送り主は田舎の母である。乾いた泥の付いた白菜を手に台所へ。今日は寒いから鍋にしよう、奈津美はそう思ったのだった。
季節は春。冬の厳しい寒さがやっと和らぎ、少しずつ温かくなり始めた頃。それでもまだ、時折冬を思わせる寒さが襲ってくる日があるもので。今日はそんな夜だ。奈津美はさっくりと、丸々届いた白菜へと刃を立てる。半分は冷蔵庫へ、そう思っていたのだが。その思考すら田舎の冬の大地のように、真っ白になった。……いたのだ。白菜の中に、先住民が。
その先住民はやぁ、と言うわけでもなく、ただただ大人しい。白菜の白さにうまく馴染むような白い体は、奈津美の親指ほどの大きさにも見える。奈津美はその芋虫へ向け、ひぃ、っと悲鳴染みた挨拶を飛ばす。最早包丁を握ることすら出来ない。一歩間違えれば、この先住民を一刀両断していたかもしれない。中途半端に切った白菜をそのままに、縋るような気持ちで携帯電話を手に取る。1コール、2コール……、こんなことで連絡しても仕方ないかと冷静さを取り戻しかけたその時、聞きなれた声が応答する。荷物は届いたかと。
「おかーさぁぁん!」
奈津美の声は今にも泣きだしそうである。何事かと問う母に事の一部始終をあくせくと説明する。それを聞いた母はふっと電話口で浅く笑った。その笑いには、大事でなくて良かったと安心する気持ちがこもっていたのだが、奈津美には伝わらない。
「そこだけ捨てて残り食べたら?」
母は強しとはよく言ったものだ。子供を持つまでは奈津美と同じように先住民に慄いていたはずだが、母として奈津美を育てるうちに、子供の方がもっと恐ろしい生き物だと知ったのだ。勿論、恐ろしいと言っても、いい意味でだが。
一方その頃、白菜の先住民は命の危機を感じていた。温かい葉の布団が裂かれ、突然に外気に触れた表面。冷えるような気がするが、よく知った北の大地の冷えではない。助けてと母に電話をかける奈津美の声を聞き、笑う。助けて欲しいのはこちらの方だ。本来ならば、羽を得て大空を舞うはずだったのに。それはきっと叶わない。
そろそろ春も本番だ。雪解けた水がさらさらと流れ、寒々しい枝の先からは新芽が芽吹く。恐ろしいのは奈津美か、母か。それとも白菜の先住民か。密かなる初春の三竦みに気付くものは誰もいない。