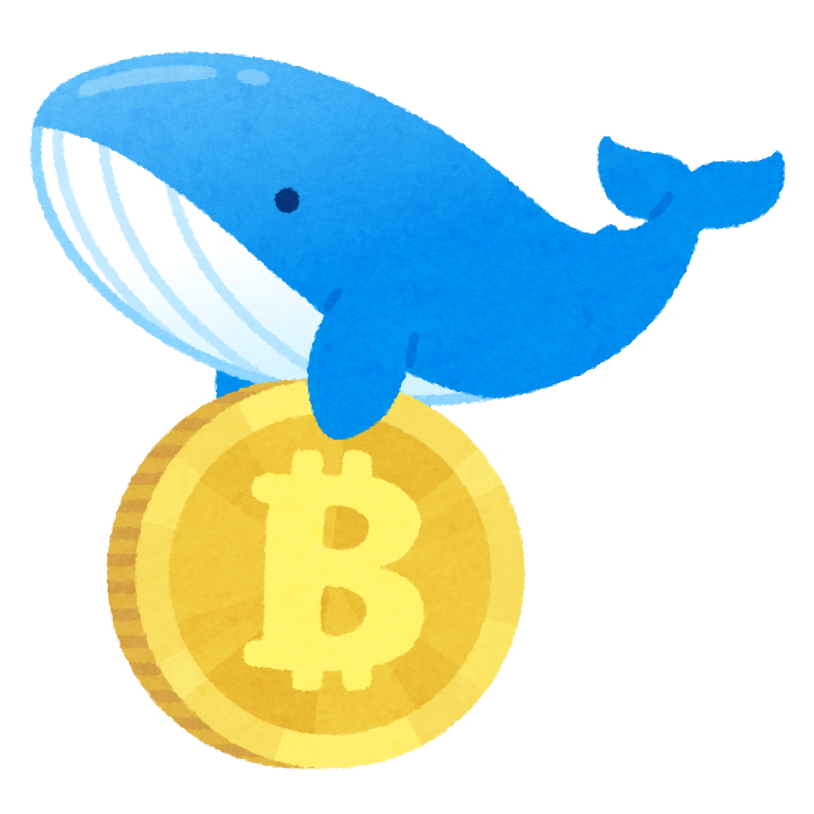作者:秋詩乃美雨 twitter
※こちらは寄稿作品です。台本作者は秋詩乃美雨(アキシノミウ)先生です。
りすの物語/秋詩乃美雨
りすは、傷を負っていました。
りすの巣の奥には、暖かい寝床も、今まで集めた木の実もありましたが、傷は深く、巣の入り口から動けず、雨風もしのげずにいました。
りすは、いつの間にか目の前にどんぐりが置かれていることに気が付きました。
いつもなら大好きなどんぐり。でも、なぜか食べる気分になれませんでした。けれど、動くことができなかったので、仕方なくそのどんぐりを食べました。
それから、いつも知らないうちに置かれているどんぐりを食べて、りすの傷は、少しずつ癒えていきました。
どんぐりがいつの間にか置かれて、それを食べて。
そんな生活が何日か過ぎたころ、りすはやっと動けるようになりました。
りすは、ゆっくり起き上がって森を見渡しました。
柔らかい光が木の葉の隙間から降り注ぎ、優しい風が頬をくすぐっていく、大好きな森です。
りすの足元には、また、どんぐりが置かれていました。
いつもどんぐりを届けてくれる相手のことを、りすはわかっていました。
それは、いつも憎まれ口を叩いてばかりいる、昔馴染みのあいつ。
どんぐりに、微かに匂いが残っていましたので、姿は見えなくても、りすには最初からわかっていたのです。
昔、「森のみんなでかけっこをして1番になったものにみんなから木の実や果物をあげる」というお祭りがありました。
誰よりも練習して、誰よりも1番になりたかったのは、この森が、誰よりも大好きなあいつでした。
自分が1番になったらみんなで持ち寄ったものをみんなで楽しく食べる、そう言って、一生懸命練習していました。
でも、1番にはなれませんでした。
たくさん、たくさん練習していました。
どれだけ悔しかったことでしょう。
いつも憎まれ口を叩いてばかりいる、昔馴染みのあいつは、勝者を称え、まるで自分のことのように喜びました。
みんなで食べようと集めていた、お気に入りの木の実も、珍しい果物も、拍手と同じように、惜しみなく、相手に贈ったのです。
りすはどんぐりを抱きしめました。
いつも素直じゃなくて、憎まれ口を叩いて、でも、すごくいいやつの、
微かに残った匂いに、感謝をしながら。
それから数日後のこと。
りすの傷は癒えてきましたが、チクチク、ズキズキと痛みは続いていました。
森は、ずっと雨でした。
辺りはうす暗く、風に揺れる木々はざわざわと、それを貫くように誰かの遠吠えが聞こえます。
りすは、だんだんと、心細くなっていく気持ちを隠せなくなりました。
遠吠えの主の姿は見えません。
きっと遠い場所にいるのでしょう。それなのに、りすの耳にはひどく大きく聞こえ、耳に残るその声は、頭の中で何度も何度もこだまするように、りすをどんどん不安な気持ちにさせるのでした。
その何者かもわからない声は、どこか懐かしい気がしました。
りすは、不安と懐かしさの中に、悲しみが隠れていることに気が付きました。
遠吠えを聞くたび、悲しみは少しずつ大きくなっていきました。
ある日、大きな葉っぱの傘をさして、くまがりすのもとへ遊びに来てくれました。
すっかり元気がなくなったりすの様子を見たくまは、何も言わず、優しく微笑みました。
くまは木の幹に腰掛けて、しばらく森を眺めたあと、ゆっくりと、いつもの穏やかな声で、りすではなく、遠くに出来た水たまりを眺めながら、りすに語りかけました。
冷たい風、止まない雨。恐ろしい声。
君は小さい。
すっかり変わってしまったこの森に、さぞ震えたことだろうね。
怖いかい?
一つ、お願いがあるんだ。
いつもの、君が大好きだったこの森を、忘れないでほしい。
僕と君が出会ったこの森、たくさんの仲間と一緒に楽しく笑った日々。
柔らかな木漏れ日に、頬を撫でる風。
くまはゆっくりとまばたきをしてから、りすを見つめました。
そして、初めてくまとりすが出会ったときとおんなじ優しい笑顔を向けると、雨の中、ゆっくりと帰っていきました。
りすは、嬉しくて、嬉しくて泣いてしまいました。
雨は、くまと会った日にようやく止んで、その日の夜の森はとても静かでした。
りすは、久しぶりに巣の奥の暖かいところで眠りました。
どんな夢をみていたのか、クスクスと楽しそうに笑っていました。
「よく寝た」と、りすは巣の外に顔を出しました。
外はまだ夜で、星たちがキラキラと輝いていました。
いつもの森。いつもの夜。いつもの星たち。
りすは、すっかり元通りになったと思っていました。
きらめく星たちに包まれて、今まで抱いたことのない思いが溢れてきました。
あの、キラキラ光る星を掴んでみたい。
りすは、巣を飛び出しました。
星を追いかけてぐんぐんと森を駆け抜け、木々をかわし、草むらをすり抜けて、やっと拓けた場所に出ました。
湖だ。
まるで星が落ちてきたみたいに、水面に星が映っていました。
りすは、星たちが本当にそこにあるように見えました。
そして息も整わないうちに湖に飛び込んだのです。
目の前の星を掴めないまま、りすの体はどんどん沈んでいきました。
不思議と苦しくも怖くもありませんでした。
大好きな森で出会った仲間たちとの、楽しい思い出が浮かんでは消えてゆき。
手を伸ばせば姿を隠し、まばたきをするとまたきらめく。
星たちは、沈むりすを追いかけるように一緒に沈む。
「あぁ、楽しかった」
りすは、そっと目を閉じました。
(間)
柔らかい光が差し込み、森の木々が風に揺られて楽しそうに歌う音に、りすは目を覚ましました。
巣の入り口にはいつものどんぐり。
りすはふかふかの地面をゆっくりと歩きながら、夢に出てきた湖に向かいます。
水面には、柔らかな光が反射していました。
りすはすこしドキドキしながら水面を覗き込み、そしてハッとしました。
りすの黒目がちの瞳に、小さいけれどキラキラと輝く星が映っていたのです。
りすは嬉しくなりました。
湖からの帰り路、いつもの森がいつもより輝いて見えました。
季節の移ろいを知らせる風が、優しくりすの頬をくすぐりました。
(間)以降エンディング選択、読まなくても良い
(おやすみりす)
いつの間にか、森に冷たい風が吹いていました。
歩き疲れたりすは、落ち葉の上でそっと眠りました。
黒目がちの瞳から、小さな星がひとつ零れ落ち、それから二度と、目を開けることはありませんでした。
(あそぼうりす)
いつの間にか、森はあたたかい色に染まる季節でした。
ふと、りすが振り返ると仲間たちが優しい笑顔でこちらを見ていました。
「おおーい、一緒に遊ぼう」
りすは大好きな仲間がいる、大好きな森の、みんなの元へ駆けていきました。